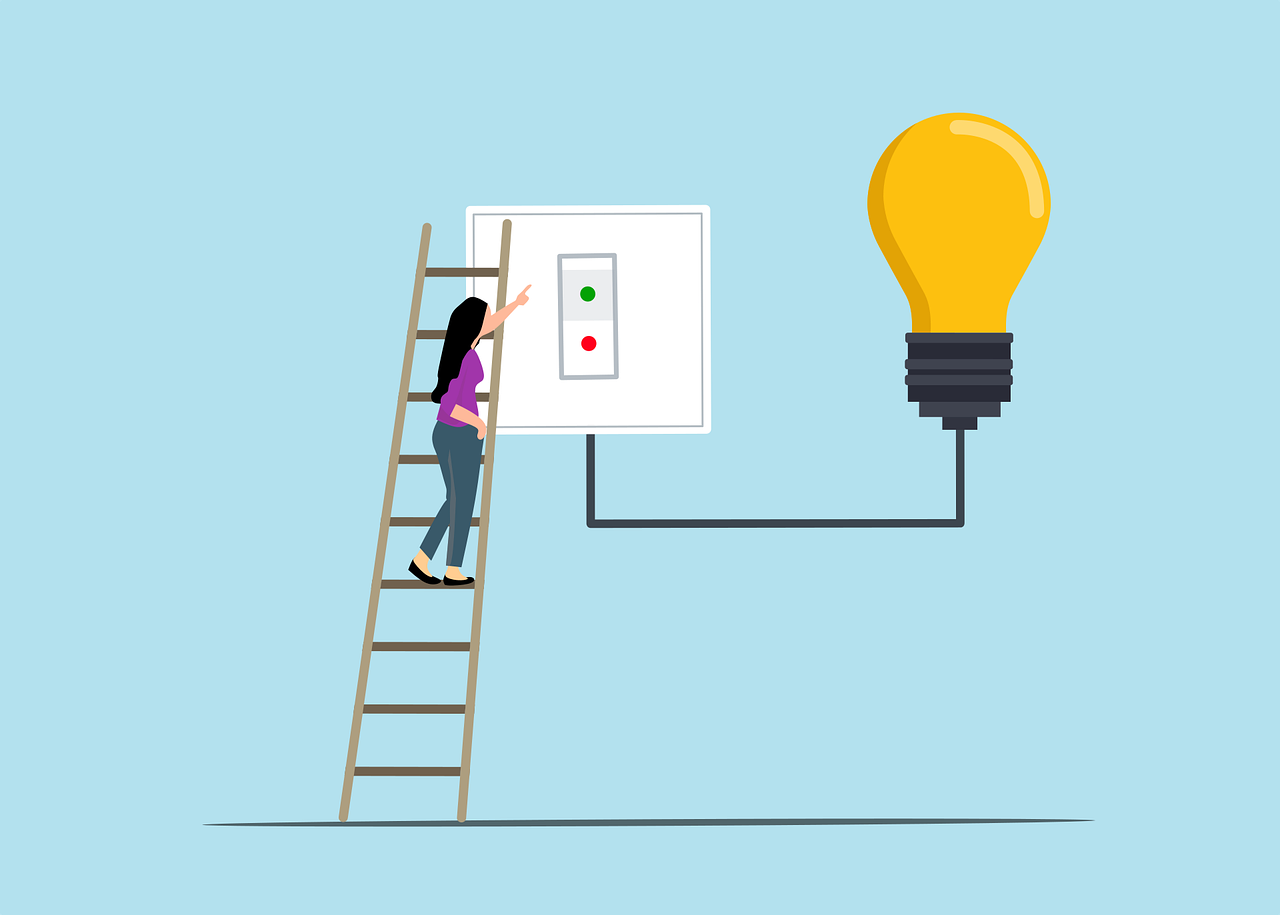さて、ここでいよいよ「レベニューマネジメントシステム」の登場です。先に述べた通り、レベニューマネジメントシステムに明確な定義はありません。先にご紹介した価格巡回システムやレポート、BIツールをレベニューマネジメントシステムと呼称するにはかなり無理がありますが、それ以上を備えていてベンダー自ら「レベニューマネジメントシステムです」と紹介している場合でも、その仕組みや機能性、機能の洗練度は大きく異なります。ただ、私は一概にこれらに「良い、悪い」があるとは申しません。「この機能があるから良い、ないから良くない」「この機能があるからレベニューマネジメントシステムである、ではない」といった観点ではなく、施設として実現したいことや現在行われているビジネス活動の形に沿うか、レベニューマネジメントの専門家として勤務しているレベニューマネージャーがそのシステムの作りや考え方、仕組みに納得するか、自信を持って運用できるかという点がより重要で、そういった点で、そのシステムの選定にはそれぞれの施設の嗜好も大いに含まれてくると思っています。従って、ここではどのベンダーの商品が良い、悪いといったことをご紹介する意図はありません。一般的に「レベニューマネジメントシステム」と自ら呼称しているシステムが備えている、または備えているべき機能をここでご紹介し、皆さんの判断材料の1つとしてご提供したいと思っています。
「どのようなシステムをどのような基準で選んだら良いのかわからない」といった声は多くの施設から聞こえますが、レベニューマネジメント関連のテクノロジーを選ぶときに忘れてはならない観点があります。それは「レベニューマネジメントにテクノロジーが導入されたからといって、レベニューマネジメントの黎明期から先人の知恵によって蓄積されてきたそのセオリーが(少なくとも今の時点では)変わることはない」という点です。テクノロジーといっても何も構えることはありません。いくつかのベンダーはAIだ、人工知能といったいわゆる「はやりの言葉」を羅列することによって皆さんを圧倒してこようとするかもしれません。しかし、実際は「そのプロセスに人工知能が使われている」というだけで、「人工知能によってプロセスそのものが変わっている」訳ではありません。つまりレベニューマネジメントとしてやらないといけないこと、注意を向けなければならない情報、またはそのやり方/プロセス/手順に変わりはなく、その過程で人工知能が使われることによってそのプロセス自体がより洗練されている(されるべき)というのがその本質です。先に「レベニューマネージャー自身がそのシステムの作り方や考え方、仕組みに納得するか」と述べたのはこの点で、検討しているテクノロジーがレベニューマネジメントのセオリーに則った仕組みになっているかという点は、システム選定の際の重要な、そしてある意味わかりやすい判断基準の1つになっているとも言えます。
a. フォーキャスト(需要予測)
まずレベニューマネジメントシステムとして必ず備えていてほしい、なおかつ1番重要である機能はフォーキャストです。繰り返しますが、レベニューマネジメントに例えテクノロジーが入ってきたとしても基本的にレベニューマネジメントのセオリーが変わる訳ではなく、施設として行うレベニューマネジメント活動の仕組み自体が大きく変わる訳でもありません。すなわち、それは正確なフォーキャストを立て、そのフォーキャストによって販売活動を組み立てていくというプロセスです。
レベニューマネジメントシステムが導入されていようといまいと、正確なフォーキャストを立てることはレベニューマネジメントの根幹です。正確なフォーキャストが立てられなければ、次のステップとしてそれをもとに考え出される販売料金等の販売活動全般の計画も立てることができません。そういった意味で「正確なフォーキャストを立てることができる」という点は、レベニューマネジメントシステムそのものの信頼性、優位性を決定する非常に重要な要素であると言えます。
まず、テクノロジーの有無に関わらず皆さんは普段どのようにフォーキャストを立てていますか?フォーキャストの重要性は以前にも何回も述べてきましたし、その種類についても詳しく説明してきました。Art and Science、フォーキャスト(1)でご紹介している通りフォーキャストにはいくつかの手順、ステップがあり、その基礎は「ディマンドフォーキャスト」です。まずはディマンドフォーキャストで総需要(アンコンストレイントディマンド/制限のない需要)を把握し、それを踏まえた上で、施設の客室数などを鑑みたコンストレイントディマンド/制限のある需要のフォーキャストである「レベニューフォーキャスト」に落とし込んでいくのが、レベニューマネジメントにおけるフォーキャストのセオリーです。このプロセスにテクノロジーの有無は関係ありません。テクノロジーがその真価を発揮できる、また自らの優位性を主張できるとすればそれはあくまでも「ディマンドフォーキャストの質」、「レベニューフォーキャストの質」といったその洗練性においてであり、プロセスそのものを変えるという事ではありません。
また、そのプロセスの一部として、そのシステムが「どのようにフォーキャストを立てるのか」という点も非常に重要です。レベニューマネジメントでは、フォーキャストはマーケットセグメントごとに立てるのが定石です。そういった意味で、マーケットセグメントごとにフォーキャストを立てるのか、いきなり全体のフォーキャストを出すのかといった違いは、結果的に出力されるフォーキャストの正確性とその質に大きな影響を及ぼします。ここで気を付けたいのは「別にマーケットセグメントごとにフォーキャストを出さなくても、最終的に全体のフォーキャストが正確であれば問題ないのではないか?」という問いです。フォーキャストは、何も「正確なフォーキャストを出すため」だけに行うわけではありません。フォーキャストを知ることで、今日から到着日までの「ビジネスの形成のされ方」を知り、それを販売活動につなげていくために行うものです。あくまでもその結果として正確なフォーキャストが重要な訳で、ただただ最後に当たっていれば良いというものではありません。(一方「施設の運営、現場、オペレーション側からの要求」という観点では、人員配置などを検討するうえで「最後に当たっている」という点は重要であると言えます)
さらに、部屋タイプごとに需要が異なるという点も、皆さんが良くご存じの通りです。スタンダードルームとスイートの需要が同じであると考えることに無理があるのと同様、部屋タイプごとに需要の積み上がり方も大きく異なります。そういった点で、部屋タイプごとにフォーキャストをするという点も重要であると言えます。部屋タイプごとに需要をつぶさに把握することで、上記同様、それは部屋タイプごとの販売の仕方、つまり到着までの販売活動の計画に大いに役に立ってくることは言うまでもありません。つまり、マーケットセグメントごと、部屋タイプごとなど「ビジネスの構成要素ごとに、粒度細かいフォーキャストを、その道すじも含めて正確に出せるかどうか」という点は、レベニューマネジメントシステムそのものの優劣を決定づける重要な要因であると言えます。
余談ですが、このフォーキャストについて面白い比喩を用いて表現している方がいました。英語では「予測すること」をフォーキャストと言いますが、似たような単語で「見込みを立てる」という英単語もあり、これをプリディクト/Predictと言います。日本においては、この「予測する」と「見込みを立てる」をあまり意識して使い分けることはないかもしれませんし、しばしばフォーキャストを見込みと表現することすらありますが、英語の用法においてはこのフォーキャストとプリディクトは明確に区別して使用されます。例えば、宿泊施設の需要予測をする時にプリディクトという単語は決して用いません。一方で、このプリディクトという単語は、例えばカジノなどで当たり目などを予想する時に使用される単語で、逆に同様の場面でフォーキャストという単語は使用しません。そういった点で、フォーキャストとはあくまでも科学的アプローチ、数理的計算という手順に依って導き出されるもの、他方のプリディクトは勘や経験、運といった要素を多分に含んで導き出されるものとして使用されるという違いがあるように思います。「全体のフォーキャスト一括で出す」という仕組みはあくまでもプリディクトの域を出ずに、そのプロセスや構成要素、粒度、道筋をもきちんと描き出してこそのフォーキャストと言えるのかもしれません。
フォーキャストを例に取ると、レベニューマネジメントシステムとして「フォーキャストをすること」が良いのではありません。システムの有無やその良し悪しに関わらず、レベニューマネジメントにとってフォーキャストをすることは当たり前で、しかも最重要項目の1つです。システムを選定する際は、単にフォーキャストをするという点だけでなく、どういう仕組みでフォーキャストを行っているのか、どのような粒度でフォーキャストを行っているのか、そのフォーキャストは道すじも含めて正確なのかという点について、実際にレベニューマネジメントに携わっている皆さんがその特徴を把握し、判断していくといいと思います。フォーキャストを提示するためのプロセスとしてディマンドフォーキャストをしないのであれば、なぜ、どういう理由でディマンドフォーキャストをしていないのか、省いているのかをぜひ聞いてみるといいと思います。マーケットセグメントごとにフォーキャストをしないのであれば、なぜ本来のレベニューマネジメントのセオリーに沿ったやり方が行われていないのか、それで正確なフォーキャストを出すことができるのかという点を突き詰めてみてください。その説明に皆さんが納得できるのであれば、それは少なくとも検討に値するシステムであるのだと思いますし、常日頃からレベニューマネジメント業務を行っている皆さんがその仕組みを理解して納得できないのであれば、それは少なくともその施設にとって良いレベニューマネジメントシステムであるとは言えないでしょう。